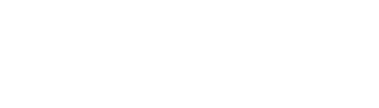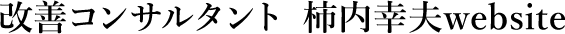-
2016.11.29
改善の発表会を開きましょう! その5 先回、日産自動車の事例を使って、変革の力は会社内にあると申し上げました。そしてその直後に伺ったT社における小集団活動発表会でそれは絶対本当だと確信いたしました。
T社では年に1回全社発表会を開きます。今回は国内5工場からはそれぞれ2件、海外の2工場は各1件で合計12件の発表がありました。私は毎年この発表会に審査員兼コメンテーター(?)として参加しているのですが、年々そのレベルが上がってきているのです。
以前は国内工場のみの参加で製造の現場改善中心でしたが、今は海外工場も参加しています。そして国内においては技術も営業も生産管理も品質管理もといった関連するスタッフ部門も参加しています。
また小集団のメンバー形成ですが、テーマによっては製造や技術や管理が一つの小集団を形成し、総合的なアプローチで相乗効果を生み出したチームも出てきました。
そして以前は活動の成果はそのほとんどが製品ごとの不良低減、生産性向上であったのですが、今ではそれらはもちろんですが、在庫やリードタイムに広がり、全社の仕組みの改善へと進歩を遂げています。
実はT社は少し前、大きな時代のうねりの中で売り上げが半分以下に激減し倒産の危機に直面しました。多くの仲間が会社を去り小集団の運営はもう無理と諦めてもおかしくない状況でした。しかしその苦しい時もこの小集団発表会は中断されることなく続けられました。今振り返ると当時、皆さんは本当に大きな不安と多くの苦しみを抱えておられました。
しかし社内のみんなで助け合い頑張った結果、業績は大幅に回復しています。最後のまとめで社長は経営の復活における従業員の皆さんの改善の成果を強調され今後の更なる改善に対する期待を述べられました。
小集団活動を止めないで本当に良かったと思いました。そしてやはり答えは社内にある!と確信した一日でした。

-
2016.11.19
改善の発表会を開きましょう! その4 先週の号外で、これからの世の中は大方の予想に反することが普通に起きるのではないかと申し上げました。
そしてその対策として、「何が起きても大丈夫な実力を付けておくことです。具体的には会社のすべての人が毎月改善を実行する習慣があるといった、変化に対して全員が自ら動くことに慣れている状態を作ることです。」と申し上げました。
そしてその具体的な方法の一つは全員が改善の実行を続けることとい言ったのですが、これに関してはかなりの確信があります。
私は25年前までの18年間、日産自動車に勤めておりました。退職後もコンサルタントとして改善のサポートをしていたことがあるので、会社が大きく変わるということをリアルタイムで見ることができました。
当時ヘロッヘロであった日産自動車にゴーンさんが社長として来てリバイバルプランを実行し、極めて短い期間に復活を遂げたことは多くの方が知るところです。ずーっと低空飛行だった日産自動車がV字回復を遂げたのですから、それは間違いなくゴーンさんの力です。
しかしゴーンさんの下で改革を実行した人はすべてそれまでの日産の人であり、大きな変化の多くの部分がその時までに準備されてきたことであることも事実です。すなわちゴーンさんの卓越したリーダーシップで引き出された大きな力は実はそれまでも社内にあったということです。
今回の結論は、社内には大きな変革に対応するに十分な力が存在するが、その多くが埋もれているということです。そしてその力を改善の発表会のなかで発見していただきたいのです。

-
2016.11.13
【号外】変化の時代にすること 大方の予想に反してトランプさんがアメリカの大統領選挙で次期大統領に選出されました。
その少し前にはやはり大方の予想に反してイギリスが国民投票でEU離脱を決定しました。
先進国代表のような米英において “大方の予想に反して” といったことが連続して起きたということは、これからの世の中は大方の予想に反することが普通に起きるのではないかと考えてもおかしくないのではないでしょうか。
すなわちこれからは今まで以上に何が起きるかわからない時代になると覚悟する必要があります。
しかし何が起きるかわからないのであれば、何をどう準備をすればいいのでしょうか?
そのことに関して私は極めて明確な答えを持っています。
それは何が起きても大丈夫な実力を付けておくことです。具体的には会社のすべての人が毎月改善を実行する習慣があるといった、変化に対して全員が自ら動くことに慣れている状態を作ることです。
大きな変化や問題が起きたらすぐにみんなが集まって対策を考え実行する。更に大きな問題が起きたらコンサルタントや近くの大学の先生や場合によってはお客様といろいろな人が集まって対策を考え実行するといったように、どんな変化や問題に対しても自ら考え改善を実行する力を持つことです。何の準備もしないでいていざとなったら何とかなるということは絶対にありません。普段からコツコツと変化に対応する練習を改善の実行を通じて行いましょう!

-
2016.11.13
改善の発表会を開きましょう! その3 先日A社であった改善発表会の様子です。その日は今年の4月に入社した5人の新人全員が、みんなの前で自分がやった改善を発表する会ということでした。
半年前に初めてみんなの前でご挨拶したときは全員ガチガチで、暗記してきた言葉を間違えずに言うので精一杯という感じだったのですが、半年経つとみんなそれぞれの職場で苦労したり努力したりの経験がモノをいうのですね、完全に会社に溶け込んでいるという風格(?)がにじみ出ていました。
さて発表ですがこれがびっくりするような立派な内容ばかりだったのです。
1.先輩が親切に仕事を教えてくれたのだけれど、実際にやってみると分からないことが出てきたので、それをすべて書き出して標準作業所の急所の欄に書き足しました。
2.先輩がいろいろな冶具の使い方を教えてくれましたが、形が似ていて区別が付きにくかったので、すべての冶具に番号をふり、それぞれの用途を書いた表を作って分かり易くしました。
3.先輩と一緒に倉庫内で掃除をして整理・整頓を行いました。不要品の廃却で分別用のゴミ箱が汚くなっていたので磨いてきれいにして表示を張り替えました。
4.先輩の作業時間と比べると2倍の時間がかかっていましたが、頑張って練習して1,3倍くらいまで近づきました。
5.先輩から声が小さいと言われたので、大きい声を出すようにしています。(先輩の応援演説付き)(確かに大きな声でした、素晴らしい! 柿内注)
実は半年前の発表会時に5人全員が半年後の発表会で改善発表をするのだと予告をされていたのだそうです。5人の新人君たちはきっとものすごくプレッシャーを感じて改善ネタを見つけ、頑張って実行して発表してくれたのだと思います。
もし新人たちに改善発表会での発表を義務付けなかったら、多分彼ら全員が改善を実行することには至らなかったと思います。そしてA社の改善はマネでもメンテナンスでもなんでもOKという緩さがあることも効いていると思います。5番目の改善なんて普通だったら改善とは言えないですよね。でもA社は働く人の努力を何より評価していますから、これでいいのです。実際にみんなが元気な声で会話をするのは大切なことですが、これを実行する方法は意外とありませんよね。A社では改善活動を使っているということです。

-
2016.11.06
改善の発表会を開きましょう! つづき 【前回お約束した具体的な方法の1回目です!】
先日出張先のホテルのエレベーターの中で起きた事件(?)についてお話しします。
そのホテルは23フロアーもある大きなホテルなのですが、小さいエレベーターが4基しかないので朝はいつもエレベーターは混雑しています。
その朝、私は20階から乗ったのですが、すでに満員状態に近く「すみません、乗せてください。」と恐縮しながらなんとか入れてもらいました。
次の階でもう一人の人が乗ってさすがに満杯になりました。しかしその後もほぼ各階に止まって扉が開いても誰も遠慮して乗らない状態で、のろのろとエレベーターは下降しました。混んでいる上に遅いので、みんなイライラしていてとても悪い雰囲気でした。きっと私もその雰囲気を作っている一人だったと思います。
そして2階に停まった時に一人の方が降りて扉が閉まりました。ようやく1階に到着と全員が思ったと思うのですが、なんとエレベーターは上昇し始めたのです。
その時です。誰かが「誰も1階のボタンを押してなかったんや!」と声を出したのですが、その言い方がとても面白く、私だけでなく数人の人が大きな声で笑ってしまいました。それ以外の人も声は出さないまでもやはり笑い顔になっているのがわかりました。
その後、そのエレベーターは全員乗ったままで23階まで戻り(ちょっとマヌケな状態ですよね)、再び下降し無事に1階に到着しました。
本来なら全員がさらにイタイラしていてもおかしくない状況だったのですが、不思議なことに一回みんなが笑ってしまうとその場の雰囲気は明らかに和やかなものになりました。降りるときは全員が「お疲れ様でした、じゃまた!」みたいな和やかな顔つきで解散(?)しました。
ここでようやくタイトルの話に戻りますが、やはり笑顔が大切です。固いガチガチの雰囲気の発表会がときどきありますが、あれやこれやの工夫をしてリラックスした楽しい雰囲気の発表会を開きましょう。

-
2016.11.01
改善の発表会を開きましょう! 【前回お約束した具体的な方法の1回目です!】

この写真は先日お伺いしたK社での改善の発表会の様子です。
K社では毎月一回、昼休み後の30分を使って数人の方がその時のご自分がやった代表的な改善をみんなの前で発表します。全員が持ち回りで一年に一回は必ず発表をすることになっています。
私は「チョコ案」という改善のやり方を提唱しています。第7話の「社長も改善」の内容がそのチョコ案なのですが、K社でもそれを実行しています。
そして皆さんが改善を継続して実行し、大きな成果を出し続けていくために是非ともやっていただきたいのが発表会です。
みんなの前で話をするのは緊張しますが、自分でやったことですから暗記は不要です。プロジェクターで映された写真を使いながら、なぜそれをやったかとか、どういう成果が生まれたかとか、苦労話などを簡単にしてもらいます。
それを聞いたみんなは、他の人がどんなことで困っているのかとか、どういう改善のやり方で結果が出たのかという情報など、普段だとなかなか伝わらない自分以外の人や部署といった会社全体のことが分かるようになります。そして最後に工場長がそれらの改善を評価し、実行者の努力をほめちぎり、今後の課題をお話しした後、全発表者にご褒美が渡されます。
人前で話をするのは苦手という方も多いと思いますが、自分で実行した改善のことですから、必ず話せます。そしてしっかり準備するとみんなにちゃんと伝わります。話す力は考える力に比例しますから、改善力がこうやって向上していくのだと分かります。こういうチャレンジをみんながすることでこれからの厳しい変化の時代に立ち向かえるのです。